節税 の記事一覧

節税しながら、資産形成しよう
【NISAとiDeCo】年内に検討すること、やっておくこと
2024年もあと1ヶ月ほどとなりました。これからNISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)を利用したい人、すで...

節税しながら、資産形成しよう
配当利回りで投資はNG?優良な「高配当株」「増配株」「累進配当株」を選ぶ3つのポイント
「配当」はどうやったらもらえる?
「配当利回り」「高配当」「増配」「累進配当」とは?
増配によって実質的な「配当利回り」が上がる理由
「配当利回り」は高ければいいわけではない
優良な「高配当株」「増配株」「累進配当株」を選ぶ3つのポイント
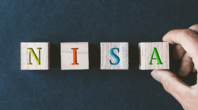
節税しながら、資産形成しよう
NISA口座で投資信託が繰上償還されたらどうなるか?
PayPayアセットマネジメントが2025年9月末での事業終了を発表
投資信託の繰上償還とは?
繰上償還されたらどうなる?
目論見書などで事前に条件をチェック

節税しながら、資産形成しよう
資産形成において投資信託のリターンを享受するには?
長期の資産形成をする上でカギを握る投資行動とは?
「トータル・リターン」と「インベスター・リターン」の違い
日本の投資家の投資行動で「正のギャップ」が観測される理由とは?

節税しながら、資産形成しよう
資産配分を元に戻す「リバランス」は定期的に行う必要があるのか?
リバランスの2つの方法、「配分変更」と「スイッチング」
スイッチングのリバランス効果を国内債券・外国債券・国内株式・外国株式で検証
リバランス検証結果、一括投資の場合は?
リバランス検証結果、積立投資の場合は?
下落相場・株価停滞に備えてリバランスをしておこう

節税しながら、資産形成しよう
新NISAの積立投資シミュレーション、「積立金額」「積立期間」「想定利回り」別の将来の資産額を早見表で確認
「毎月3,000円」「20年積立投資」「運用利回り3%」の資産額はいくら?
積立金額を増やしたら資産額はどうなるのか
積立金額・運用利回りから資産額がわかる早見表(運用期間15年・20年・30年の場合)
運用利回りを高くするのは要注意、リスク許容度に合わせて運用先を選ぶのが鉄則

節税しながら、資産形成しよう
新NISAで積立投資を始めたばかりの初心者が知っておきたい、急なマーケット変動への備えと対策
下落相場になっても、投資・運用を継続できる「家計・資産状況」であるかを確認
値動きの大きさに耐えられないなら、値動きを抑えた資産へ入れ替える
暴落が起きても、「保有&積立継続」しよう
米国株式市場、世界株式市場、共に拡大していく可能性が高い
過去データでは「15年」以上の運用継続で元本割れなし

節税しながら、資産形成しよう
ボーナスではじめる新NISA、自分に合った投資商品を選ぶ考え方
「いま使うお金」と「将来のために使うお金」に分ける
「生活費6ヶ月」の預貯金を優先、「4・3・2・1」の比率でボーナスを分配する
はじめての新NISAは「つみたて投資枠」の活用から
全ての人が投資すべき商品はない。「リスク許容度」に合わせて選ぶ

節税しながら、資産形成しよう
企業年金ありの会社員、公務員は要注意。iDeCoで毎月定額以外の納付方法を選んでいる人は変更を
2024年12月から、iDeCoの拠出限度額の算定方法が統一
iDeCoの拠出限度額変更に向けてやるべきこと

節税しながら、資産形成しよう
老後貧乏にならない「資産運用の出口戦略」
「70歳までは資産形成」が基本戦略
70歳以降は「資産の取り崩し」のフェーズ
取り崩しの合言葉は「前半は定率、後半は定額」
自分のために貯めたお金を「あの世には持っていけない」

節税しながら、資産形成しよう
2024年4月から改善される投資信託総経費率のポイントと留意点
投資信託は3者に支払われる
課題は統一基準がなくわかりにくいこと
運用報告書に加え、目論見書にも記載
見やすくなった総経費率、3つの留意点

節税しながら、資産形成しよう
60代、70代の「新NISA」活用戦略
2024年から「新NISA」が始動。主な変更点と考慮すべきポイントとは
60代の働ける間は資産形成期、退職金も有効活用
60代・70代に適した「新NISA」の運用商品とは?
高配当株を選ぶ時の5つのチェックポイント
資産運用の出口戦略とは?

節税しながら、資産形成しよう
50代共働き世帯の「新NISA」活用戦略
2024年から「新NISA」が始動。主な変更点と考慮すべきポイントとは
50代は老後資金に向けた「最後の貯めどき」
家計に無理のない範囲が鉄則。50代の運用目標は“月10万円×15年間”
資金に余裕があれば、「新NISA」の“成長投資枠”で個別株に投資も
定年後の資産取り崩し期で不安を取り除くために、不労所得を得る戦略も






