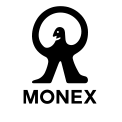日産自動車(7201)と本田技研工業(7267)の経営統合が話題
2024年12月の株式市場は、日産自動車(7201)(以下、日産)と本田技研工業(7267)(以下、ホンダ)の経営統合の話題でもちきりだったと言えるでしょう。12月18日の日本経済新聞のスクープで始まった今回の経営統合話は、日産の苦境が原因でした。販売不振に伴う決算の落ち込みや人員整理などは報道のとおりですが、特に不調ぶりが顕著だったのは株価です。
アベノミクスによる円安進行以降の2014年から2018年にかけては概ね1,000円を超えていた日産の株価は、直近では400円を割る水準まで落ち込んでいました。2023年の高値が712.5円、2023年末でも554.2円でしたが、上記の経営統合が報道される前日の12月17日には337.6円と年初来安値をつけていたのです。
日産株は報道以前より約40%上昇、ホンダ株は年末年始を挟み8連騰
統合報道を受け、12月18日に日産株は417.6円とストップ高となりました。その後、一時は500円台半ばまで買われるなど、安値から60%以上も上昇していましたが、年末年始にかけて落ち着き、1月6日の終値は475.2円でした。統合報道以前より引き続き40%程度高い水準ですが、2023年末の554.2円よりいまだ安い水準です。
一方、苦境の日産を「救済する」とされたホンダは、やや事情が異なります。ホンダも統合報道前から株価は低迷しており、年初来安値水準でした。報道等で「救済」色が出たこともあり、苦境の日産に足を引っ張られる印象があったためか、報道後2営業日は株価がさらに下落し、12月19日には年初来安値を更新しています。
しかし、その後、自社株買いの発表や記者会見などを経て、ホンダ株主の不利がないという印象が高まったためか、株価は大きく回復。12月20日以降は年末年始を挟んで8連騰、2023年末の株価を超えてきているような状況です。
日本を代表する会社同士の再編から見えてくる「株主からの影響力」
それにしても、自動車産業と言えば日本の基幹産業であり、その大手同士の再編というのは驚きです。実際、直近決算の売上高ベースで見ると、東証上場会社でトヨタが1位、ホンダは2位です。日産は9位です。その他10位以内の会社は三菱商事(8058)など商社が3社、あとはENEOSホールディングス(5020)、日本電信電話(NTT)(9432)、ソニーグループ(6758)、日本郵政(6178)ですから、まさに日本を代表する会社同士の再編です。
また、直近決算ではホンダの売上高が20.4兆円、日産は12.7兆円と、それなりに差が開いてはいるものの、もともと日産はトヨタと並ぶようなイメージであり、ホンダと日産の売上もここ10年ほどは概ね拮抗していました。その日産が「救済」されるのは非常に印象的です。
すでにトヨタの時価総額をテスラ[TSLA]が上回って久しく、中国での電気自動車の隆盛の報道などもあり、自動車業界に大きな変化が起きていることはよく言われていました。この統合はそれを体感させるニュースだったように思います。そして、この統合をスクープした日経新聞は、スクープ同日に「ホンダ・日産が経営統合へ 鴻海による買収回避へ決断」という記事も出しています。
この記事によれば、鴻海は日産自動車の買収に関心を持っており、過去の経緯で同社株を保有するルノーの日産株にも関心を示しているとのことです。この報道を見ると、引き続き株主からの圧力が日本の会社の動きに大きく影響していくことを予感させます。実際、すでに日産にはアクティビストが投資をしているという報道もありました。
時価総額2000億円超の会社の買収ニュースが相次ぐ
パロマ・リームホールディングスが富士通ゼネラル(6755)の買収を発表
年明けの1月6日には富士通ゼネラル(6755)をパロマ・リームホールディングスが買収することが発表されました。翌1月7日には同社株はストップ高水準となっています。富士通ゼネラルは名前の通り、富士通(6702)が親会社で株式を40%超保有していますが、富士通は同社株の売却を模索していたようです。これは、富士通のビジネスとの相乗効果や親子上場を課題にしていたものと思われます。パロマであれば富士通ゼネラルの中核である空調同士で合併効果が見込まれるでしょう。富士通ゼネラルは時価総額が2000億円を超える大きな会社ですが、2025年もこうした規模の会社の買収が続いていくことが考えられます。
また、2024年末にはニデック(6594)が牧野フライス製作所(6135)に公開買付を行うことを発表しています。牧野フライス側は事前に連絡を受けていなかったとのことで、同意なき公開買付ということになります。牧野フライスも時価総額が2000億円を超える会社です。
このように年末から年始にかけて、マーケットでは大きな動きが続いています。これらは今までになかったような動きに思われ、本連載で取り上げているマーケットや投資家からのアプローチの影響が加速してきているのではないでしょうか。過去に取り上げているセブン&アイ・ホールディングス(3382)の話を含め、2025年もいろいろな動きが出てくると思われます。
2025年注目したいJ-REIT、停滞が目立つ背景は?
その中で2025年に注目したいのはJ-REITの動きです。J-REITは株式とは異なり、アクティビストのプレッシャーなどを受けにくくなっています。過去の記事「J-REITの増資が投資家に嫌われる理由」でも、その問題点を取り上げています。
そうした影響もあってか、J-REITは不調が続いています。図表1のチャートを見れば分かる通り、2021年半ば以降、J-REITはほぼ一貫して下落しています。

この間、日経平均は大きく上昇しており、2023年頭までは同じような動きをしていた不動産業の株価指数も2023年以降は大きく上昇しているため、J-REITの停滞が目立ちます。

もちろん、J-REITの苦境はインフレによる管理コストの増加や不動産取得が難しくなっていること、そしてなにより日本においても金利が上昇していく中で、一定の借金を行って不動産投資をするJ-REITは不利になるという逆風の影響は大きいでしょう。
事実、日本の金利上昇を促している円安傾向が加速してきた2022年以降、J-REITの不振が目立ってきているように映ります。図表3のチャートのように、ドル高(円安)に伴って日本の金利上昇圧力がかかっていることがJ-REIT価格に影響していそうです。また、ドル高の背景に米国の金利高があるとされていますが、米国金利の上昇が米ドル建て債券の魅力を高め、同じ利回り商品であるJ-REITの不利になっているということもあるでしょう。

逆風のなかJ-REITが割安だと考える理由
2025年は日銀による利上げもささやかれており、一方で米国の利下げは想定よりも進まないとみられ、そういう意味で2025年は逆風になりそうです。ここ数年で不動産価格は大きく上昇しており、当然J-REITの保有している物件も大きく上昇しています。J-REITでは投資法人の保有する不動産などの資産価値から負債を引いたネットアセットバリュー(NAV)を出していますが、不動産価格上昇の中、このNAVは上昇しています。
このNAVを投資口価格で割ったものをNAV倍率と言います。株式ではPBR、解散価値などと言われるもので、数字が高いほど割高、数字が低いほど割安になります。NAVが上昇する中で、投資口価格は上記の通り、下落傾向なのでNAV倍率は減少傾向を強めています。結果的に上場J-REIT58銘柄中1倍を超える銘柄は3銘柄で、36銘柄は0.8倍を割っているような状況です。分配金利回りも42銘柄は5%を超えるような状況で、まさに非常に割安な水準です。
J-REITのプロフェッショナル関大介さんも、本サイトで「【REIT】J-REIT市場にも買収の動きは波及するのか」という記事を書かれています。関さんの連載「J-REIT投資の考え方」を読んでいただければ、J-REITが割安かどうかの分析がより深まるのではないでしょうか。
そもそも魅力的な5%超の利回り水準、J-REITの動向に注目
最後に、直近でおもしろい動きが出てきていることを紹介します。
制度改正により、J-REITでも自己投資口の取得ができるようになっています。現状、J-REIT価格は保有資産から見ても非常に割安な状況のため、投資法人側は自己投資口の取得を行う判断も多そうです。たとえば、2024年は1月から4月にかけて6つの法人が合計280億円の取得を発表しました。これは過去最高であった2022年の230億円(7法人)をさらに上回っており、J-REITの業界団体である不動産証券化協会がレポートで取り上げているほどでした。
4月以降もいくつかの法人が自己投資口の取得を行っていましたが、直近その動きが加速してきています。2024年10月は5法人、11月は1法人が発表を行いましたが、12月16日には1日で4法人が取得を発表、合計で135億円(上限ベース)となっています。上述の関さんの記事にもあるように、J-REITの構造はやや複雑で、買収などが簡単に起こる状況ではないのですが、保有価値と投資口価格の乖離は投資法人自体も気にしている状況のようです。
2025年になり、NISAの新しい枠も使えるようになっており、5%を超える利回り水準はそもそも魅力的に思われます。その中で、動きを期待してJ-REITに注目するのも面白いのではないでしょうか。