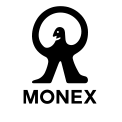【米国株式市場】ニューヨーク市場
NYダウ: 42,801.72 △222.64 (3/7)
NASDAQ: 18,196.22 △126.97 (3/7)
1.概況
先週末の米国市場は、主要3指数がそろって反発しました。寄付き前に公表された2月の米雇用統計において米労働市場の軟調さが示されたことにより、株式市場では売りが先行しましたが、パウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長が講演で米経済は引き続き好調であると発言したことで景気減速懸念が和らいだほか、このところ株式市場が大きく下げていたことも相まって、買い戻しの動きが見られました。
76ドル安で取引を開始したダウ平均は、一時403ドル安まで下げ幅を広げる場面も見られました。安値を付けた後は持ち直して上昇に転じ、上げ幅は一時319ドルまで達しました。引けにかけては上げ幅を縮めると、結局ダウ平均は222ドル高の42,801ドルで取引を終えました。
また、ハイテク株比率が高いナスダック総合株価指数は126ポイント高の18,196ポイント、S&P500株価指数は31ポイント高の5,770ポイントで取引を終えました。
2.経済指標等
2月の米雇用統計で非農業部門雇用者数は前月比15万1000人増となり、16万人増程度を見込んだ市場予想を下回りました。なお、12月の雇用者数は30万7000人増から32万3000人増に上方修正され、1月分は14万3000人増から12万5000人増に下方修正されています。一方、失業率は4.1%と市場予想を上回って前月から0.1ポイント悪化しました。また、平均時給は前年同月比4.0%上昇となり、市場予想を下回りました。
3.業種別動向
S&P500の業種別株価指数は、全11業種のうち8業種が上昇となり、なかでも公益事業やエネルギー、情報技術、資本財・サービスが1%以上上昇しました。一方で、生活必需品や金融、一般消費財・サービスの3業種が1%未満の下落となりました。
4.個別銘柄動向
ダウ平均構成銘柄では、30銘柄中20銘柄が上昇しました。なかでも、アイビーエム[IBM]が5%以上上昇したほか、ベライゾン・コミュニケーションズ[VZ]が4%以上上昇、マクドナルド[MCD]が3%以上上昇しました。また、キャタピラー[CAT]やシェブロン[CVX]、アムジェン[AMGN]が2%以上上昇したほか、エヌビディア[NVDA]やアップル[AAPL]、ハネウェル・インターナショナル[HON]など6銘柄が1%以上上昇しました。一方で、10銘柄が下落となり、特にウォルマート[WMT]が3%以上の下落となりました。また、ボーイング[BA]が2%以上下落したほか、ジェイピー・モルガン・チェース[JPM]やゴールドマン・サックス[GS]、ホームデポ[HD]、セールスフォース[CRM]が1%以上下落しました。
ダウ平均構成銘柄以外では、半導体のブロードコム[AVGO]が3月6日の通常取引後に公表した第1四半期決算で、市場予想を上回る売上高とEPS(1株当たり純利益)を達成し、第2四半期のガイダンスでも市場予想を上回る売上高見通しを示したことで8.6%上昇し、S&P500株価指数構成銘柄の値上がり率トップとなりました。また、アパレルのギャップ[GAP]は、2025年2月通期の業績が市場予想を上回る増収増益となり、良好な見通しを示したことで18.8%上昇しました。一方、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ[HPE]は、第1四半期の業績が増収、営業減益となり、通期利益見通しが市場予想に届かなかったほか、約3000人の人員削減計画も発表したことで12%近く下落し、S&P500株価指数構成銘柄の値下がり率ワーストとなりました。また、コストコ・ホールセール[COST]は、第2四半期決算で増収増益を達成したものの、EPSが市場予想に届かず、6.1%下落しました。
5.為替・金利等
米長期金利は前日から0.02%高い4.30%となりました。ドル円は、147円台後半で推移しています。
VIEW POINT: 今日の視点
本日の日本市場は、先週末の米国市場が反発した流れを引継ぎ、上昇してのスタートが予想されます。こうしたなか、日経平均は心理的節目の3万7000円台を回復した後、どれだけ上げ幅を広げられるかが注目されます。特に、先週末の米国市場ではフィラデルフィア半導体株(SOX)指数が3%以上上昇と好調であったことから、日本市場でも半導体関連銘柄の買いが期待されます。
また、今週は米国で12日に消費者物価指数(CPI)、13日に生産者物価指数(PPI)と物価指標が相次ぎ公表される予定で、これらの結果を受けた長期金利や為替の動きに注目が集まります。なお、米国市場は3月10日(月)の取引から、標準時間(冬時間)からサマータイム(夏時間)に移行します(https://info.monex.co.jp/news/2025/20250226_02.html)。
(マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 岡 功祐)