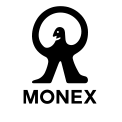【米国株式市場】ニューヨーク市場
NYダウ: 42,967.62 △101.85 (6/12)
NASDAQ: 19,662.49 △46.61 (6/12)
1.概況
昨日の米国市場では、主要3指数が揃って小幅に反発しました。寄付き後は、中東情勢の悪化に対する警戒感やトランプ政権の関税政策を巡る不透明感から下落する場面も見られました。一方で、米PPI(生産者物価指数)が市場予想を下回る結果で、利下げ期待が高まったことに加え、個別株でオラクル[ORCL]が決算で発表した見通しが人口知能(AI)需要の強さを示し、ハイテク株や半導体株の一角に買いが入り相場を支えました。
ダウ平均は128ドル安の42,737ドルで取引を開始すると、一時259ドル安まで下げ幅を広げ、42,606ドルでこの日の安値を付けました。安値を付けた後は反転し、取引終盤にかけて上げ幅を広げていくと104ドル高の42,970ドルで高値を付けました。最終的に101ドル高の42,967ドルと高値圏で取引を終え、反発となりました。
また、ハイテク株比率が高いナスダック総合株価指数は46ポイント高の19,662ポイント、S&P500株価指数は23ポイント高の6,045ポイントで取引を終え、いずれも小幅に反発しました。
2.経済指標等
5月の米生産者物価指数(PPI)は、前年同月比で2.6%の上昇となり、市場予想と一致しました。前回の2.5%上昇からは伸びがやや加速しています。また、前月比では0.1%の上昇となり、前回結果(0.2%低下)を上回ったものの、市場予想(0.3%)は下回りました。
一方、変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアPPIは、前年同月比3.0%上昇となり、市場予想と前回結果(ともに3.2%上昇)を下回りました。また、前月比では0.1%上昇となり、前回結果(0.2%低下)を上回ったものの、市場予想(0.3%)を下回りました。先週一週間までの新規失業保険申請件数は、前週と同水準の24.8万件となり市場予想を上回りました。
3.業種別動向
S&P500の業種別株価指数では、全11業種のうち8業種が上昇となり、特に公益事業と情報技術が1%超上昇しました。一方で、コミュニケーション・サービスや一般消費財・サービス、資本財・サービスの3業種が小幅に下落しました。
4.個別銘柄動向
ダウ平均構成銘柄は30銘柄中19銘柄が上昇となりました。特に、ユナイテッドヘルス・グループ[UNH]が2%超上昇したほか、アムジェン[AMGN]やメルク[MRK]、トラベラーズ・カンパニーズ[TRV]、エヌビディア[NVDA]、シスコシステムズ[CSCO]、マイクロソフト[MSFT]が1%以上上昇しました。一方で、11銘柄が下落となり、特にボーイング[BA]は4%超下落しました。インドで12日に同社の中型機が墜落したことが悪材料視されました。また、スリーエム[MMM]やベライゾン・コミュニケーションズ[VZ]、ウォルマート[WMT]は1%以上下落しました。
ダウ平均構成銘柄以外では、オラクル[ORCL]が13.3%上昇し、S&P500株価指数構成銘柄の値上がり率ランキングでトップとなりました。同社は、第4四半期決算で売上高とEPS(1株当たり純利益)が市場予想を上回ったほか、2026年通期のガイダンスで力強い見通しを示したことが好感されました。ヘルスケア事業者や製造業者にサービスを提供するカーディナル・ヘルス[CAH]は、2025年度通期のEPS見通しを上方修正したうえ、市場予想を上回る2026年度通期の見通しも発表したことが好感され、4.6%上昇しました。
一方、GEエアロスペース(ゼネラル・エレクトリック[GE])は、ボーイングの事故機に同社製エンジンが搭載されていたことが伝わり、2.3%下落しました。また、アパレル企業のオックスフォード・インダストリーズ[OXM]は、第1四半期決算で売上高とEPSが市場予想を上回ったものの、第2四半期のEPS見通しが予想を大きく下回ったことや、通期のEPS見通しも下方修正されたことが嫌気され、13.9%下落しました。
5.為替・金利等
米長期金利は、前日から0.06%低い4.36 %で取引を終えました。ドル円は、円高方向に進展し、143円台半ばで推移しています。
VIEW POINT: 今日の視点
昨日の米国市場では主要3指数が揃って小幅に反発となりました。一方で、外国為替市場では円高方向に進展していることが輸出関連の主力株には逆風になると考えられ、強弱材料が交錯し本日の日本市場は小動きでのスタートが予想されます。日経平均は今週、一度も3万8000円を割り込んでおらず、この水準を維持したまま週末を迎えられるかに注目が集まります。本日は、国内で4月の鉱工業生産指数の発表が予定されており、相場の手掛かり材料となりそうです。
(マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 岡 功祐)