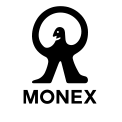2025年6月6日(金)21:30発表(日本時間)
米国 雇用統計
【1】結果: NFPは市場予想を上振れし失業率は4.2%と横ばい 平均時給も予想超え
5月の米雇用統計で非農業部門雇用者数は前月比13万9000人増となり、市場予想を上回りましたが、前月の14万7000人増からは伸びが鈍化しました。なお、3月分は18万5000人増から12万人増へ、4月分は17万7000人増から14万7000人増へとそれぞれ下方修正されています。
失業率は4.2%となり、市場予想通り前月から横ばいとなりました。小数点第3位まで比較して見ると、前月は4.187%、今月は4.244%とやや悪化しています。平均時給は前月比+0.4%、前年同月比+3.9%と、いずれも市場予想を上回りました。賃金の堅調な伸びが続いており、インフレとの関連にも引き続き注目が集まります。

【2】内容・注目点:「解雇はされないが再雇用もされにくい」現在の労働市場
非農業部門雇用者数はまずまずの伸び
5月のNFP(非農業部門雇用者数変化)は、前月比13.9万人増となりました。関税政策などによる不確実性が高まる中、米労働市場に対して悲観的な見方も広がっていましたが、結果は10万人台半ばとまずまずの伸びと評価できます。一方、過去2ヶ月分は計6.5万人分下方修正され、図表2の6ヶ月移動平均を見ても、米国の労働市場は緩やかな減速トレンドにあることが確認できます。

民間部門が雇用増を主導
非農業部門雇用者数変化の内訳(図表3)を見ると、民間部門の雇用者数は14.0万人増、政府部門は1,000人減と、民間部門で雇用が増えている点は良好と言えます。

DOGEの人員削減により連邦政府職員は前月比2.2万人減
政府部門全体は前月比で1,000人減少しましたが、その中でも連邦政府職員は2.2万人減と大幅に減少しました。これは「政府効率化省(DOGE)」による人員削減の影響とみられます。また、図表4に示す通り前年同月比で見ても、連邦政府職員数はマイナス圏に突入しています。
こうした動きは2017年のトランプ政権下にも見られましたが、当時は2022年の中間選挙に向けて増加に転じた経緯があります。今回も同様であれば、2026年の中間選挙を意識して、1年半後には人員削減の方針が転換する可能性があります。

民間部門での関税の影響は小売など流通業に
民間部門では、小売業界の雇用が6,000人減少し、2ヶ月連続の減少となりました。現状、米CPI(消費者物価指数)などの指標では物価上昇は確認されておらず、関税の影響に対しては小売・卸売など流通業がマージンを削ることで対応していると推察されます。その結果、利益率の低下に対処するため、人員削減の動きが出ているとみられます。
また、関税の影響を直接受けやすい貿易・輸送・公益事業を見ると、関税導入前の駆け込み需要もあり、今のところ雇用増が確認されていますが、今後は反転減少となるか動きに注目が集まります。
失業率は横ばい。理由別の内訳に注目
家計調査に基づく失業率は前月から横ばいの4.2%となりました。失業理由別の動向を見ると、景気後退と強く関連する「恒久的失業」(図表5の赤線)の割合は前月からほぼ変わらず、上昇傾向は一服しています。
一方で、いったん労働市場から離れた後に再び労働市場に戻ってきた「再就職者」の失業率(図表5の黄土色線)は上昇傾向が続いています。また、転職などを目的に自ら仕事を辞めた「自発的離職者」の失業率(図表5の緑線)は減少傾向にあります。

JOLTS統計によれば、解雇率は依然として歴史的低水準にとどまっている一方で、雇用率や離職率も低い水準が続いており、現状の労働市場は「解雇されにくいが転職や再就職もしにくい」という均衡状態が続いていると読み取れます。

前述のような均衡状態の中で雇用者数の伸びが鈍化しているにもかかわらず、失業率が横ばいで推移している背景には、移民など外国生まれの労働者が足元で減少していることから、労働供給の減速が影響していると考えられます。(労働供給が減ることで、一定の失業率を維持するために必要な雇用者数は少なくなる)

【3】所感:雇用の悪化ペースはFRBの想定通りか
今回の雇用統計では、NFPが市場予想を上回り、失業率も横ばいと、総じて安心感のある結果となりました。過去2ヶ月分の下方修正があったものの、現在の雇用増加ペースは、3月のFOMC時点でFRBが想定していた巡航速度に近く(図表8参照)、現時点では労働市場に大きな問題はないと評価できます。(失業率の悪化は往々にして急速に進む傾向があり、関税の影響も導入後にタイムラグを伴って表れると考えられるため、引き続き予断は許されない状況にあります)

労働市場に大きな問題がない場合、FRBは物価指標に集中できるようになります。6月11日、12日に発表される米CPI(消費者物価指数)、PPI(米生産者物価指数)に注目です。
フィナンシャル・インテリジェンス部 岡 功祐