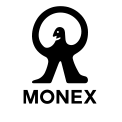2025年5月13日(火)21:30発表(日本時間)
米国 消費者物価指数(CPI)
2025年5月15日(木)21:30発表(日本時間)
米国 生産者物価指数(PPI)、小売売上高
【1】結果:インフレ指標鈍化、小売売上高は前月から伸びが減速



【2】内容・注目点:関税の初期影響は?
CPI、財価格の上昇は見られたがスーパーコア中心にインフレ鈍化を示す
相互関税の影響が懸念されていた中、4月の総合CPIはインフレ減速を示す結果となりました。
図表4の通り、総合CPIの寄与度を分解すると、原油価格の低下を背景にエネルギー(青緑色バー)が押し下げ要因となったほか、これまでインフレをけん引してきたコアサービス(黄土色バー)も着実に低下基調にあることが確認できます。

サービスインフレの鈍化は、政策金利が高水準で維持される中で、住居費が緩やかに低下してきたことを反映しています。
先行きについては、CPIの住居費に約1年先行するとされるジロー価格指数やS&Pケース・シラー住宅価格指数の動向を踏まえると、今後も緩やかな下落または横ばいで推移する可能性が高いと考えられます(図表5)。

一方、住居費は遅行性が強く、FRB(米連邦準備制度理事会)が金融政策を考える上でも取り扱いがやや難しい品目のため、FRBのパウエル議長はコアサービスから家賃を除いた「スーパーコア」に注目しています。
そして、4月のスーパーコアは前月比+0.21%となり、前月からは上昇したもののコロナ前の平均と同水準にとどまりました。また、前年同月比では+2.7%と前月の+2.9%から低下しています(図表6)。

一方、気になる関税の影響ですが、関税の影響を受けやすい商品価格に初期の影響が見られており、コア財価格(前年比)は、2023年12月以来16ヶ月ぶりにプラス圏に浮上しました(図表7)。

CPIの先行指標となるPPIは鈍化
PPIは、原材料や製品を対象として生産段階での財・サービスの価格変動を測定するもので、CPIの先行指標とされます。そして、4月のPPIは予想以上の低下を示し、ヘッドラインの数値からは今後のインフレ圧力の低下が示唆される結果となりました(図表8)。

図表9の通り内訳を確認すると、CPIと同様に関税の影響を受けたコア財価格は上昇した一方で、サービス価格が低下していることが確認できます。また、FRBが金融政策のインフレ指標として重視する個人消費支出(PCE)価格指数の算出に用いられる項目は、総じて抑制的な結果となりました。
これらはインフレ目標の観点からポジティブと言える一方、気になるのは流通業(小売・卸売業)のマージン手数料が前月比で大幅に下落したことです。この項目の低下は、関税強化による財の輸入価格の上昇分を、流通業がマージンを削ることで負担していることを意味します。消費者負担を和らげるという意味ではポジティブと言えますが、流通業の利益率の低下やそれに伴う雇用悪化が懸念されます。

力強さに欠ける小売売上高
図表10の通り、4月の小売売上高は、13項目中5項目で増加し、3月の11項目増加を大きく下回りました。

また、図表11の通り、米国消費の基調的な強さを表し、GDPの算出に用いられるとされるコントロール・グループ(自動車、ガソリン、外食、建設資材を除いた小売売上高)の推移を見ると、依然として底堅さを維持しているものの、トレンドが下向きに反転していることが分かります(図表青色線)。
これまでの米国消費は無店舗小売が全体をけん引してきた側面がありますが、ここのところ力強さに欠ける印象で、図表11の黄色バーが占める割合は縮小しつつあることが分かります。

【3】所感:流通マージンの低下に懸念
4月のCPI、PPIは、関税の初期影響が財価格に見られたものの、全体としてはインフレ圧力の抑制が確認され、ひとまず安心感のある結果となりました。しかし、流通業のマージンが減少している点に注目すると、企業は現時点で原材料価格の上昇分を消費者価格に転嫁せず、企業努力により吸収していると推察されます。
ウォルマート[WMT]のダグ・マクランCEOは決算発表で「可能な限り低価格を維持するが、小売りマージンが少ないため、全てのコスト上昇を吸収するのは困難」と述べており、財価格を中心とした今後の消費者価格の上昇が懸念されます。
ここで焦点となるのは、消費者が価格上昇についていけるかどうかです。直近の小売売上高の推移を見ると、底堅さは維持されているものの、トレンドは反転しつつあり、先行きにやや不透明感が漂います。消費者が価格上昇についていけなくなれば、企業収益の低下を招き、それが雇用悪化を引き起こす可能性があります。雇用の悪化は購買力(需要)の低下をもたらし、これが負のスパイラルを引き起こせば、景気後退につながるリスクも否定できません。
こうした状況を踏まえると、一般物価全体としてはデフレリスクの台頭も懸念され、パウエルFRB議長も関税の影響が本格化するまで様子見の姿勢を取っているように、金融政策の判断は一層難しい局面に差し掛かっています。
フィナンシャル・インテリジェンス部 岡 功祐