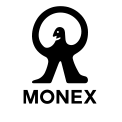J-REIT、2025年に入ってから値動き好調
J-REIT指数は3%程度上昇
前回の記事「2025年はJ-REITに注目か? 日本企業はマーケットからの影響が強まる」では、J-REITを取り上げました。自己投資口取得を進める例が散見されるなど、J-REITが投資家利益の施策を進めていることに注目しました。
2025年に入ってから、J-REITの値動きは好調で、1月27日時点で日経平均が2024年末から値下がりしているのに対し、J-REIT指数は3%程度の値上がりで推移しています。前回記事の時点から現在も継続して、自己投資口取得を進めているJ-REITは5銘柄ありますが、その5銘柄はいずれも2024年末比で上昇しています。
自己株(J-REITは自己投資口)の取得を行っている会社(投資法人)はその取得状況を定期的に報告しますが、この5銘柄はいずれも12月に自己投資口を買い付けています。取得を行わないようなケースもある中で、確実に取得していることは投資口価格の安定にも直接寄与していそうです。
総合型のJ-REIT 、KDX不動産投資法人(8972)を分析
現在、自己投資口を取得しているJ-REITの中で最も時価総額が高いKDX不動産投資法人(8972)(以下、KDX)を見てみると、発行済の投資口は約400万です。2024年12月に発表した取得決議では53,000口、全体の約1.3%の投資口を取得しようというもので小さくありません。実際に、12月は年末にかけて8,694口を取得したとのことです。
同法人の取得決議は12月17日に開始したため、12月17日から12月30日の10営業日しか投資口を取得していません。この間の東証でのKDXの出来高は合計で90,000口強でした。このうち、8,694口は自己投資口取得なので、東証での取引の約1割を買い上げているわけです。自己投資口取得が小さくないということを、ご理解いただけるのではないでしょうか。実際、12月16日に144,200円だった投資口価格は上記の10営業日で5,300円と、4%程度値上がりしており、値上がり日が7、値下がり日は3となっています。
上記のような取引動向の分析は開示資料から簡単に行うことができます。現在、自己投資口取得を行っている5銘柄の比較なども容易です。これはJ-REITの取引水準が比較的小さく、値動きが安定していることによるものでしょう。
また、J-REITは基本的には不動産保有のみを事業としており、その投資方針や保有物件、物件の稼働率や各物件の投資金額・収益動向など、かなり細かく開示されています、そのため、一般の会社に比べて個人投資家でも分析がしやすく、例えば、KDXの場合、webサイトでも以下のように分配金履歴が簡単に確認できます。

前回の記事では、「2021年半ば以降、J-REITはほぼ一貫して下落しています」と解説しました。これはJ-REIT指数をみての話でしたが、KDXはどうだったのでしょうか。
KDXの2021年半ば(2021年6月末)の投資口価格は195,750円です。2025年1月27日時点の終値が152,300円なので、実に20%以上下落しています。しかし、まさに図表1のように、KDXの分配金は直近の2024年10月期が最も高い水準で、2021年6月末が属する2021年10月期から見ると、ほぼ一貫して上昇しているのです。
分配金は基本的にはJ-REITの利益水準に連動するので、これは1つの例ですが、ここ数年、利益・分配金が伸びる一方で、投資口価格が伸び悩んでいることがよく分かります。KDXは総合型のJ-REITなので、居住用施設を取得価格ベースで27%保有しており、その多くは東京都、たとえば佃島や豊洲、代官山、半蔵門、戸越、恵比寿といったエリアに物件を保有しています。都内の住宅価格や賃料が上昇傾向なのはその通りでしょう。個々の物件データも開示されているので、分析してみてはいかがでしょうか。
フジ・メディア・ホールディングス(4676)のメディア・コンテンツ事業は以前より停滞、不動産ビジネスは救世主となるか?
フジ・メディア・ホールディングスはそもそも「不動産事業」で賄う会社
さて、不動産と言えば、最近注目されるフジ・メディア・ホールディングス(4676)(以下、フジ・メディア)も不動産保有の会社として知られます。もともとサンケイビルというグループ会社が上場しており、同社を買収したこともあって、フジ・メディアの2024年3月期の売上高の22%、利益の54%を都市開発・観光セグメントが稼いでいます。
フジ・メディアはそれら不動産に加え、リクルートホールディングス(6098)などの優良株も保有しています。この連載でも、2021年に「時価総額ランキングに変化!保有株式の価値が大きな企業を見分ける方法とは」「意外な不動産資産の保有会社は?」などの記事で、保有株式や保有不動産に注目し、取りあげたことがありました。
上記2021年の記事で帳簿価格2314億円、時価2743億円(含み益400億円強)としていたフジ・メディアの賃貸不動産ビジネスは、2024年度末の決算では帳簿価格3361億円、時価4050億円(含み益700億円弱)と拡大しています。株価も上昇傾向で、上の記事で取り上げた「その他有価証券評価差額金」も1170億円と高水準を維持しています。
各種報道等にあるように、フジ・メディアを巡る問題が取り沙汰される中で、主要子会社のフジテレビのCM出稿が停まっており、フジテレビはその部分の広告費を同社が負担するなどとしています。当然、売上に対する影響は小さくはないでしょう。一方、これもよく知られているように、伝統的な会社は本業の落ち込みを不動産事業などで賄っており、もともとテレビ事業自体がインターネットメディアの伸長の中で弱体化しつつあったフジ・メディアは、典型的な不動産事業で賄う会社だったと言えそうです。
今回の騒動がなくても本業のメディア・コンテンツ事業は不振の状況
実際、マネックス証券の「銘柄スカウター」を見ると、フジ・メディアのメディア・コンテンツ事業は停滞しており、2022年から2024年にかけてセグメント利益は230億円から157億円に減少しています。都市開発・観光は同時期に111億円から195億円に伸びており、まさに本業の減益を不動産で賄っている形です。

直近決算の2024年3月期は典型的で、メディア・コンテンツ事業は128億円の増収ながら、17億円の減益となっています。都市開発・観光事業の増益44億円で、それを賄っています。メディア・コンテンツ事業の減益はフジテレビが22億円の減益となっており、フジテレビ以外は4億円の増益でした。メディア・コンテンツ事業の中でもコンテンツは好調だったものの、テレビが不振ということです。今回の状況がなくても厳しい傾向だったと言えるでしょう。
実際、コロナ前の2019年3月期に2679億円の売上(営業利益は102億円)であったフジテレビは、2024年3月期には2382億円の売上(営業利益は54億円)と、売上高で300億円近く減少しているのです。この間、営業利益が50億円の減益で済んでいるのは、コスト削減などに取り組んだためでしょう。逆に言うと、5年間で300億円の減収であれば、コスト削減などである程度縮小均衡を進められ、それでも減益する分は不動産事業に支えられていたわけです。
年間売上2000億円超のメディア・コンテンツ事業のショックを不動産ビジネスで賄えるのか?
一方、改めて数字を見ると、フジテレビの年間2000億円を超える売上というのは非常に大きいことが分かります。前述したように、都市開発・観光ビジネスの利益は195億円と伸びてきているものの、まさに桁が違います。もちろん、売上と利益ではあるのですが、今回フジテレビの売上そのものが大きく減少しているので、かなりの部分は利益にも影響が出そうです。
フジテレビの2382億円の収入のうち、1834億円は放送・メディアによる売上です(それ以外はコンテンツ・ビジネス)。年間で1834億円、四半期でも450億円以上の売上がフジテレビの放送事業であがっており、仮にこの売上が毀損するとなれば、いかに都市開発などで賄おうとしても賄えない計算になります。都市開発・観光事業の利益は四半期で50億円の水準だからです。
フジ・メディアは利益で言うと、都市開発・観光が大きく、メディア・コンテンツを上回るのですが、売上高、つまりビジネス自体のサイズで言うと、メディア・コンテンツが圧倒的で、その中核がフジテレビになるのです。

フジテレビの業績はこの5年で10%程度の売上減少がありました。それに対し、利益は50%程度の減少となっています。もちろん、5年であればその間にコスト削減もできるので影響が小さいのですが、売上減の利益への影響の大きさは分かると思います。
これが短期に起きると、利益への影響は大きく、都市開発・観光で賄うのも容易ではない可能性があります。フジ・メディアは不動産などの資産で魅力のある会社ですが、サイズは本業が大きく、本業が徐々に縮小するのであれば十分に他の資産で賄えますが、大きなショックがあった場合は、本業のサイズやその影響に特に注意すべきでしょう。
USスチール買収同様、投資判断にもアクティビストの影響強まる
さて、今回のフジ・メディアを巡る動きはご存知の通り、アクティビストがフジ・メディアに対し書簡を送ったことが大きな展開につながったように思います。上記のような資産を考慮してアクティビストが投資していたのでしょう。
直近では、日本製鉄(5401)のUSスチール買収についても、アクティビストがUSスチールに対して、日本製鉄との合併を断念するように提案する動きが出ています。様々な大きな事象に対し、アクティビストの与える影響が増してきており、今回のフジ・メディアを巡る一連の動きはまさにそういうものだったように思います。投資判断にあたっては、その影響をよく分析する必要があるでしょう。