3年前に書いた【マネックス証券入社2周年記念レポート】「光と波」は、PART1~3の3部からなる大作で、僕自身は相当な思い入れをもって執筆したが、読者の評判は散々だった。レポートの一部を引用しよう。
<山口: ガウス分布のときは
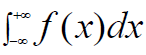
でしょう。ガウス分布のときはその分布をfとするとすべてのnについてこれが全部有限で存在するわけですか、+∞では指数的に小さくなるから。平均から分散まで無限次のエレメントが全部有限である。一方、ジップの法則ではランクサイズというやつがランクが無限に右のほうに行ってもエクスポネンシャルで減少しないのでバリアンスも存在しない、積分が有限でない。>
(寺本英・広田良吾・武者利光・山口昌哉「無限・カオス・ゆらぎ」)
学者同士は宇宙人の言葉で話していればよいが、これを一般読者向けに解説するのが僕の役目だ。僕がおこなった「翻訳」は以下の通り。
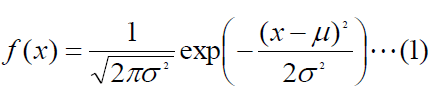
<この確率密度関数は釣り鐘型のベルカーブを表す。カーブの左端と右端はマイナス∞(無限大)から+∞で決してx軸には接しない。無限大までいくということは限りなくゼロに近いから、事実上x軸に接したものと捉えてもいいかと言うと、それは否である。正規分布であっても裾野はずっとどこまでも延びて決してx軸には接しない。裾野の問題はその値が収束するかという話である。無限までいっても、その値自身は有限の値をとることがあり得る。例えば
1+1/2 +1/4 + 1/8 ... (1 + 1/2 + 1/22+ 1/23+ 1/2n ...)
の合計値は2になる。その数列が無限まで続いても計算できるのだ。正規分布の分散が計算できるのは、収束する度合いが速いので上手く計算できると考えたほうがいい。なぜ正規分布が速く収束するかと言えば、式(1)の通り、exp(エクスポネンシャル)で割っているからである。(中略)
すごく急激にカーブが上昇するもの(つまり指数的に増大するもの)で割るのだから速く収束するのである。山口先生が言っている「+∞では指数的に小さくなるから」とか「無限に右のほうに行ってもエクスポネンシャルで減少しない」とはそのことである。正規分布は「無限に右のほうに行くとエクスポネンシャルで減少し」収束するが、ジップなどのベキ分布は「無限に右のほうに行ってもエクスポネンシャルで減少しない」のでサンプルのとりようによっては分散が発散してしまうのである。>(【マネックス証券入社2周年記念レポート】「光と波」PART2)
3年経った今、こうして読み返してみても、かなりうまく「翻訳」できていると、悦に入っているのは僕ひとりであって、読者からしてみれば完全に「置き去り」にされた気になるだろう。
プロの書き手は自分が書きたいものを書かない。読者が読みたいものを書くのである。「ゴルゴ13」のさいとうたかを氏もそうだし、代表作「すべてがFになる」で知られるベストセラー・ミステリー作家・森博嗣氏もそういう発言をしている。
マネックスに入社し、この仕事を始めて5年になる。僕も少しは成長したところを見せないと、この厳しい競争社会で淘汰されてしまう。自分が書きたいものでなく、読者が読みたいものを。この世界株安を前にして、個人投資家がいちばん知りたいことは、何だろう。それは、おそらく、この世界株安の背景とこの先どうなるかという予測だろう。それを簡潔に伝えればいいのではないだろうか。
世界株安の背景は何か。2つの可能性が考えられる。ひとつは、何も理由がない、というものである。なにをバカな!と思われるだろうか。これほどの世界同時株安に理由がないなんてことがあるか!とお怒りの読者もおられよう。しかし、株価というものは何も理由がなくても下げるものである。しかも大幅に下げることもある。典型例が1987年10月19日に起きた「ブラックマンデー」だ。その日、NYダウ平均株価は前日比で22%超の大暴落を記録した。それから30年近く経つ現在でもまだブラックマンデーが発生した明示的な原因は究明されていない。
市場に不安材料は確かにあった。インフレ懸念が醸成されるなか、米国の双子の赤字が増加していたこと。プラザ合意以降のドル安に対する国際協調の乱れ - 特にドイツが米国の反対を押し切って利上げに踏み切ったことで緊張が高まっていたこと、そしてFRB議長がボルカーからグリーンスパンに変わった直後だったこと、などである。しかしそれらは、遠因となったかもしれないが、なぜ「1987年10月19日」という特定の日に前日比2割を超すような未曽有の大暴落が起きたのかということの説明にはならない。暴落を引き起こすような特別な「事件」は何も起きていなかったのだから。
ひとたび市場で売り圧力が高まると、当時流行していた「ポートフォリオ・インシュランス」というリスク管理プログラムによって下げが拡大した、ということは多くの分析があり解明が進んでいる。しかし、それは下げを加速させた要因の一つではあっても、暴落そのものを引き起こした原因では、やはりないのである。
ブラックマンデーの暴落直後、3人の経済学者がある調査をおこなった。デイヴィッド・カトラー、ジェイムズ・ポターバ、そして著名なローレンス・サマーズの3人である。彼らは、目に見える原因が一つもない大規模な市場変動は実は頻繁に起きていて、ブラックマンデーの暴落はそのなかで特に激しいケースに過ぎないのではないか、と考えた。彼らは株価変動の大きかった日を50日分取り出して、その株価変動の原因となったとみられるようなニュースがあったかどうかを検証した。その結果は、株価全体の変動の半分しか説明できていなかった、というものであった。
また、同様の研究を2000年にイエール大学のレイ・フェア教授がS&P500先物の変動について調べたところ、変動率の大きかった全1159件のうち、変動をもたらしたと思われるニュースに紐づけられたケースは69件、わずか6%未満という結果であった。
こうした調査結果をもとに、アカデミックな世界では、「株価は材料がなくても変動する」というのは、いまや明白な事実と認識されている。
「材料がなくても」というのは言い過ぎかもしれない。「材料が特定できなくても」下げることがある、という表現の方が正確だろう。そして、この「材料が特定できない」ということは、「わからない」ということと同義であり、市場にとってのリスクは「わからないこと」である。だから、なぜ下げたのか理由が明白で特定できる(わかっている)下落より、なぜ下げたのか理由が特定できない(わからない)下落のほうがリスク度合いが高いということになる。
これを証明したのが、物理学者のアルマン・ジュリアンとジャン=フィリップ・ブショーが率いる研究チームである。彼らはナスダック上場の900社以上の株式データとダウ・ジョーンズやロイターなどが提供する2年分、数10万件に及ぶニュースを使って、明らかにニュースに関連した大きな株価変動と、そうした関連性がない大きな変動とを選び出した。そして両方のケースについて、大きな変動が起こってから数時間後の変化を観察した。彼らが観察したのはボラティリティの推移だ。突然株価が動くというのはボラティリティ(変動率)がジャンプする(高まる)ということだが、そのジャンプしたボラティリティは時間の経過とともに通常の状態に戻る。その戻る時間を両者について比べたところ、ニュースと関連性のある事象の方が、ニュースと関連のない事象よりも、はるかに短かったのである。
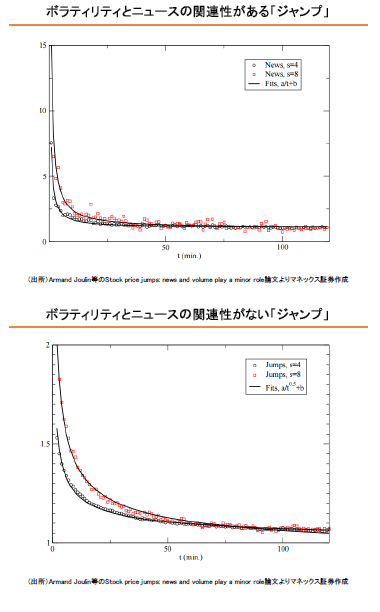
その理由について、ジュリアンとブショーの研究チームはこう推察している。
ニュースと明確な関連がある株価変動の高まりは、背景が理解可能であるがゆえに、驚かず、少なくとも狼狽することはない。ところが、(フラッシュ・クラッシュのように)ニュースと関連のない株価の急変動は、説明がつかない不可解さがつきまとい不安になる。それこそ真のショックである、というわけだ。
市場では、右も左も「中国景気減速で世界株安」との報道であふれている。市場関係者ほぼ全員に「中国不安」⇒「世界株安」という「因果関係」(に見えるもの)が刷り込まれている。
しかし、仮に「中国不安」がこの株安の原因であると、本当に市場参加者の全員が盲信的に思っているとすれば、これほどまでに市場の動揺が収まらないのはなぜか?ジュリアンとブショーの研究によれば、理由が特定できればボラティリティは速く収束するはずである。その結果は直感的にも理解しやすい。そうであるならば、これほどまでにボラティリティが高止まり続けるという、その事実自体が、今回の世界株安の理由を市場がまだ特定できていないことの証明ではないだろうか。
今日でマネックスに入社して丸5年。僕も成長した。読者の望むものを提供するようになったのだ。読者から寄せられる批判でいちばん多いのは、「レポートが長過ぎて読む気にならない」というものだ。このあたりで第一部、PART1は筆を置こう。しかし、2015年版「光と波」はまだまだ続きます。世界株安の背景として2つの可能性が考えられる、と上述した。次回、PART2では、もうひとつの可能性について所見を述べたい。そして、2015年のアップデートとして、市場の「光と波」を描写したいと考えている。
