今週7/28-29の金融政策決定会合を控え、市場では経済対策と金融緩和策の全力投下への期待が高い。しかし我々は、今回の決定会合では、追加緩和は、資産購入対象の拡充とETF購入枠拡大等、やや規模の小さいものに留まるとみている(図表1)。

足元で消費者物価指数は、日銀の「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」は鈍化し(図表2)、一橋大学の週次データ等即時性のあるデータでは既にマイナス基調となっている(図表3)。今回は財政政策も同時並行で進んでいるため、財政支出の副作用(理論的には円高)をオフセットする必要もある。これらのことから、今回の金融政策では"ゼロ回答"はないものの、手段の温存や、副作用の大きさから、ごく限定的な政策に留まるとみている。
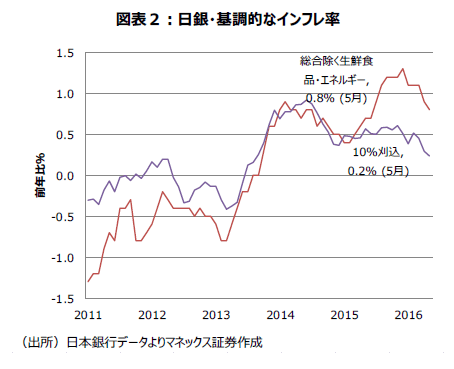
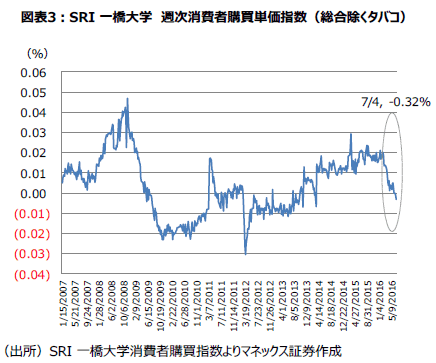
特に、市場の期待も大きいマイナス金利の深掘りについては、後述の通り、まだ効果がみえず、副作用も大きいため可能性は低いとみる。そもそもこの手法が市場で期待されている大きな理由は、手段として取り得る"余地"が大きいことである。しかし、その効果が不透明なのに"やりやすいのでやる"、というのはやや無理筋にも思える。今後、米国の大統領選、欧州の金融リスク等海外市場の不透明要因に備え、数少ないカードを温存するという意味でも、マイナス金利の深掘りは次回以降に含みを持たせる程度となる可能性が高いと考える。
マイナス金利影響の現状と、その深掘りのリスク 今のところ、マイナス金利導入後、貸出ボリュームへのプラス効果等は殆どみられない。どころか、むしろ、マイナス金利導入後は伸びが鈍化している印象である(図表4、5)。これに呼応して、マネーストックの伸びも、マイナス金利導入後はやや伸びが鈍化している(図表6)。

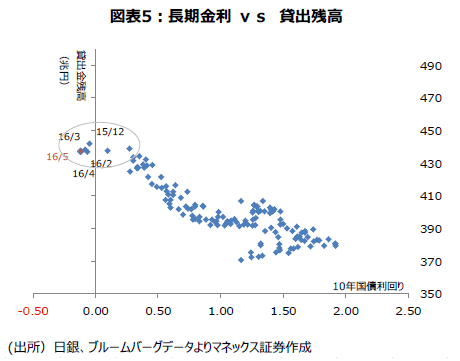
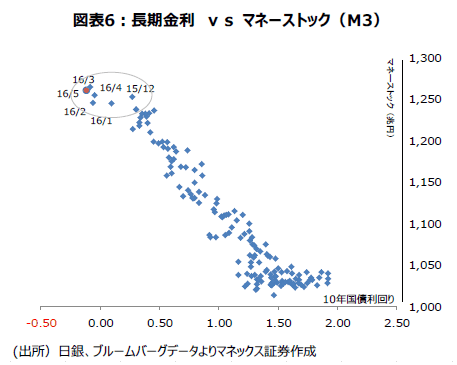
また、センチメントに対してのマイナス影響も払拭できていない。弊社の金融政策決定会合に関する事前アンケート(7/22~25実施、個人投資家298名が回答)でも、マイナス金利深掘りを予想する声は少なく(図表7)、また、もしマイナス金利が深掘りされた場合、投資意欲は「減退すると思う」という回答が前回6月調査から増加する一方、「高まると思う」という回答が大きく減少している(図表8)。


銀行への副作用:マイナス金利深掘りは、導入時を大きく超える打撃 更に日銀当座預金金利のマイナス幅が拡大した場合、銀行へのデメリットは、マイナス金利導入時よりはるかに大きい。今回金利が引き下げられても、もう前回のような預金金利の引き下げ余地は殆どない。従って、貸出利回りの低下は銀行の収益をもろにヒットする。
また、企業向け貸出の基準金利であるTiborだけでなく、これまでほぼ無傷だった短期プライムレートも引き下げられる可能性が高い。短期プライムレートは中小企業向け貸出や住宅ローンの基準金利になっており、地銀では、貸出全体の約半分の金利がプライムレート(大半が短期プライム)に連動している。
これらによって、大手行の場合、当期利益が更に5.9%程度低下する可能性がある(図表9)。問題は地銀であるが、仮に短期プライムレートを20bp引き下げざるを得なくなった場合、利益は2割も下落する可能性があるだろう。
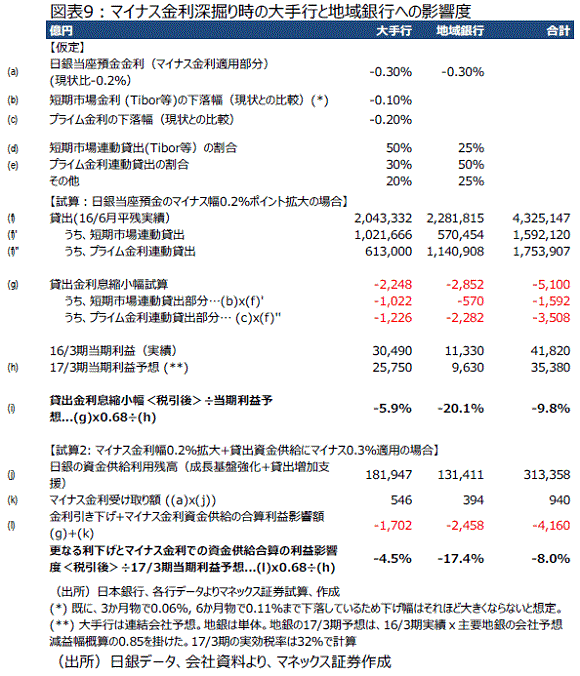
こうした背景から、銀行収益への悪影響を緩和するため、日銀の資金供給枠の適用金利をマイナス金利に引き下げて恩恵を与えるという可能性がある。しかしそれでも、図表10の通り、マイナス影響は相殺しきれない。マイナスでの資金供給の銀行利益に対する効果はせいぜい1.5~3ポイント程度となるだろう。しかもここには、マイナスで資金供給した場合に想定される副次的マイナス影響、例えば、企業が銀行に対する貸出金利の引き下げ要求を行うという懸念などは織り込まれていない。

このシナリオでは、銀行としても、いよいよ一般企業にまで預金口座管理手数料の導入を検討せざるを得ないだろう。そうなれば企業のセンチメントを更に冷やしかねない。
マイナス金利の唯一の顕著な効能としては、企業の調達の長期化が挙げられる。図表11の通り、マイナス金利導入後の5か月で、期間20年以上の超長期債の発行額は4,020億円と久々の勢いとなっている。しかしこうした長期資金も、優良企業における銀行の取引関係を長期に固定することになることから、新たなメイン行争いの場として金利競争に浸食される可能性が高いだろう。
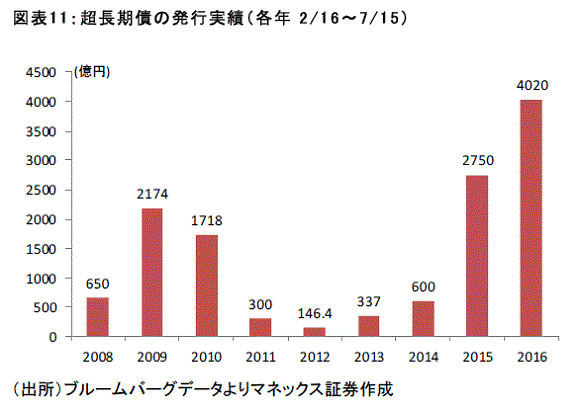
とりうる選択肢:資産購入枠拡充:効果は大きくなくても、ゼロ回答よりはベター 量的緩和の拡充については、買入対象資産範囲の拡大(例えば、買入対象社債の年限を3年から10年に長期化、買入対象に例えば地方債、各種政府機関債を加えるなど)を行い、その分購入目標も若干拡大する(例えば現在の年80兆円増加から100兆円まで引き上げる)などの政策が考えられる。
一般に資産購入枠拡大は限界であるとする根拠として、国債の売り手が減少していることが挙げられる。実際、銀行の残高保有額は昨年末に13年ぶりに10%を切り、絶対額も100兆円を切っている(図表12)。ただ、比率ほどには絶対額は減少しておらず、更に、担保として使われるとされる外貨調達についても預金の増加や(図表13)、外債の発行も進んでいるため、まだ多少は国債売却の余地はあるだろう。 更に、買入対象を、欧州のような地銀や政府機関債等国債以外の債券に広げれば、(大きくはないものの) 十兆円余の買入枠拡大の余地は残されているだろう。
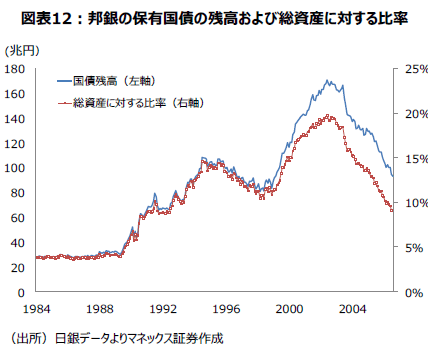
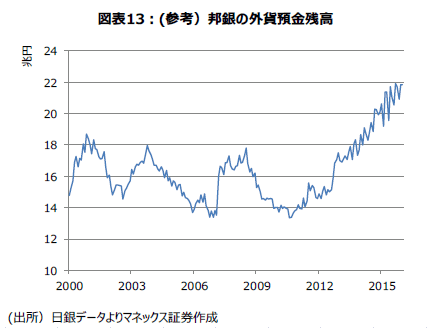
なお、超長期債や永久債の発行と日銀によるその直接引受け(いわゆるヘリコプター・マネー)が行われる可能性は極めて低いだろう。この政策は、国の信用力に関わる重大事である上、一度とったら極めて「不可逆的」である。一旦開始したら、市場がクラッシュするまで停止することは難しい。通常の量的緩和も後戻りしにくくはなっているが、政府の財政拡大意欲に抵抗しなければならないヘリマネほどの劇薬ではなく、まだ「可逆的」である。
ETF/JREIT購入枠拡大 ETF/J-REIT購入枠の拡大については、手段としての余地は残されており、市場のセンチメントを改善することなどから相応に可能性はあるだろう。しかし、そもそも株式は企業収益から導かれる理論価値があるにも関わらず、その価格を需給面で引き上げ続けることは、常に市場を「割高」に引き上げかねないため、無尽蔵に取れる施策ではないと考える。
財政政策との関係 このような金融政策の調整の市場に対する効果は限定的だろう。しかし、何もしない場合は、財政政策のマイナス効果(円高等)の懸念が生じるため、実行の意味はある。
そもそも現在報道されている経済対策は、事業規模こそ20~30兆円と大きいものの、国費(真水)の追加額は2兆円程度(来年度以降分を含めて6兆円)に留まる。真水の金額としては、過去の規模から突出するものではない(図表14)。ゆえに、金融政策で補正しなければならないような為替リスク等もある程度限定されるだろう。
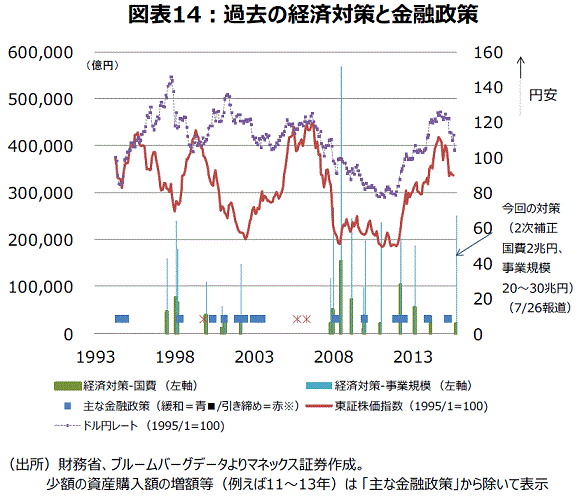
まとめ これらの政策が取られた場合、市場の期待感が先行していることから、一段の上値を求めるのは厳しいだろう。特に、最近持ち直してきた銀行株については、政策がすぐにインフレ期待に働きかけるとは考えにくく、方策次第では収益への直接的な打撃が大きくなりうることから警戒が必要と考える。
