ジョンブル(イギリス人のこと)は、たいていのことは我慢するが、2分の利子率には我慢できない (ジョン・メイナード・ケインズ)
雇用統計で遠のく利上げ観測
先週金曜日、日本時間の夜9時30分。米国の雇用統計が発表された。その時間に僕は東京大手町の日経新聞本社ビル20階にある日経CNBCのスタジオにいた。一緒に番組に出演していたエコノミストの第一声は、「ほっとしました」。
誰もが同じ気持であっただろう。1カ月前に発表された非農業部門の雇用者数の伸びは市場予想の半分にも満たなかった。それだけでなく1-3月期の経済指標は総じて冴えないものばかり。果たしてそれらは天候要因や西海岸の港湾ストの影響なのか?あるいは本当に米国の経済成長に翳りが生じているのか?1-3月期は減速しても、4-6月期には再び成長を取り戻すという見方がコンセンサスだが、4月の雇用統計次第では、その見方も修正を迫られるところだった。だから、発表された雇用統計の内容が、事前の市場予想にほぼ沿う格好だったことで多くの市場関係者が胸をなでおろしたのであった。
雇用統計を受けて米国株式市場は上昇した。ダウ平均は267ドル高の1万8191ドル。上昇幅は2月3日以来ほぼ3カ月ぶりの大きさだった。一方、債券も買われ10年債利回りは低下した。平均時給の上昇率が前月比0.1%と、0.2%を見込んだ市場予想に届かなかった。非農業部門の雇用者数は前月比22万3000人増と市場予想とほぼ同水準だったが、前月分が大幅に下方修正された。前月があまりにネガティブ・サプライズだったから市場予想並みで安心感が広がったが、冷静に見れば決して強い内容ではない。少なくともFRBに利上げを急がせるような雇用統計ではなかった。債券が買われ、金利は低下し、対ユーロを除いてドルも弱くなった。早期の利上げ観測が後退した結果だ。ざっくり言って、株式市場の上昇の半分程度は、やはり利上げ警戒感の緩和によるものではなかろうか。
イエレン議長の懸念
米国の長期金利が上がらない。前回のレポートで指摘した通り、ユーロ安の反転が様々なポジションのアンワインド(巻き戻し)を誘発し、ゴールデンウィーク前後の資本・金融市場は大荒れとなった。なかでも債券市場の急落(金利の急騰)はすさまじいものだった。米国の10年債利回りも一時2.30%にワンタッチ、年初来最高水準まで切り上げた。しかし、再び債券市場は落ち着きを取り戻しつつあるようだ。前述の通り、雇用統計を受けて利上げ観測が後退し10年債利回りは再び2.1%台に低下した。3月のピークと併せてWトップを形成しているようにも見える。
イエレン議長は先日、現在の米国株式市場について「現時点で株式市場のバリュエーション が総じてかなり高くなっている」と述べた。FRBの利上げに伴い、現在は異例に低い水準にある長期金利が「急速に動く可能性がある」とも語った。
市場に対する警鐘であることは明らかだ。グリーンスパン元FRB議長が1996年12月、ITバブルへとひた走る米国株式市場を「根拠なき熱狂」と評し、警鐘を鳴らしたことを引き合いに出す向きもある。しかし、ここで注目すべきは、単なる株式市場の割高感ではない。
そもそも株式市場の割高・割安を語るならば、その基準を示さなければ議論にならない。「根拠なき熱狂」という言葉は、「根拠から大幅に乖離した」という意味である。バリュエーションの議論には根拠が要る。一般的なバリュエーション指標であるPER(株価収益率) - 株価がEPS(1株当たり利益)の何倍まで買われているかを測る尺度 - は、S&P500で17倍である(12カ月先予想EPSベース)。1985年から現在まで過去30年の平均は約15倍弱である。
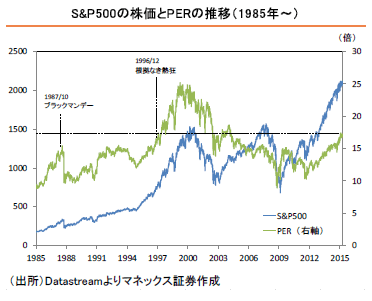
過去の平均から比べれば現在の17倍というPERは高いと言える。ちなみにグリーンスパン元FRB議長が「根拠なき熱狂」と述べた1996年12月のPERは16倍程度だった。1987年のブラックマンデー前は、8月につけた15倍台がPERのピークであった。確かに高いが、「かなり高い」かどうかは見方が分かれるところだろう。
金利見合いのバリュエーション
「ここで注目すべきは、単なる株式市場の割高感ではない」と上述したのは、イエレン議長が株式の割高感と債券利回りの低さを同時に言及したからである。PERの逆数、すなわち株式益利回りは株式市場の期待リターンと捉えることができる。益利回りと債券利回りの差を「イールドスプレッド」といい、株式の期待リターンと債券のリターンとどちらが魅力があるかを測る指標として使われる。利益成長を考慮しない静的なバリュエーションモデルにおける株式のリスクプレミアムと見ることもできる。
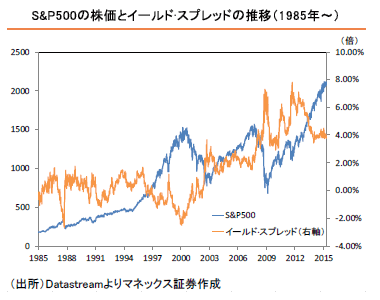
イールドスプレッドの1985年から現在まで過去30年の平均は1.5%であるのに対して、現在は3.8%である。つまり、金利見合いのバリュエーションという観点では株はまだ割高ではなく、歴史的にプレミアムがたっぷり上乗せされた状態であり、むしろ割安と見ることさえできるかもしれない。
僕の口癖をご存じの方も多いだろう。それは「どんなものにも2つの面がある」ということだ。インフレにも良い面、悪い面があり、円高にも良い面、悪い面がある。そして通貨の交換レートである為替も円の要因で動く場合もあればドルの要因で動く場合もある。「円安でなくドル高である」などと言われたりする。
イールドスプレッドについても同じことが言える。これは株式が割高でないのか、あるいは金利が低すぎるのか?われわれはこの議論をさんざん繰り返してきた。ざっくりとした感覚で(英語で「ガッツ・フィーリングで」)言えば、株はバブルの入り口、債券は既に超バブル - そんなところだろう。株式は「かなり割高」ではないが、明らかに「割安」ではない。一方、債券は異常に買われ過ぎているため、現在の超低金利を基準に物事を評価するのは大変危険である。
ウォーレン・バフェットも同様のことを述べている。バフェットは自ら率いる投資会社、バークシャー・ハサウェイの年次株主総会で、「米国の金利が現在の超低金利水準から通常の金利に戻れば、現在の価格にある株式が高く見えるだろう」という見方を示した。
異常な低金利が是正される時、株式市場の割高感が強烈に意識されることになる。それが、この先のグローバル金融市場最大の波乱リスクであろう。ただ問題は、果たして米国の長期金利が上昇する時が来るのだろうか?
ターム・プレミアム
前掲したように、イエレン議長はFRBが利上げに動けば長期金利は上昇すると言うが、ここまで異常に低い金利は社会経済の構造問題に起因するという説もある。実際に、米国は前回の利上げ局面に、長期金利が上がらないという「異常事態」を既に経験している。2004年6月~06年6月の2年間、FRBはFOMCを開催する度に25bpsずつ、累計4.25%もFFレート(政策金利)を引き上げたが、その間に長期金利はほとんど上昇しなかった。「根拠なき熱狂」でその慧眼を示したグリーンスパン議長に「Conundrum(謎)」と言わしめた事象である。市場で決められる長期金利が上昇しなかったことで、FRBの金融引き締めの効果は限定的となった。それが住宅バブル・クレジットバブルの発生を許し、サブプライム問題を生む温床となった。その帰結がリーマンショック、未曽有の金融危機につながったことはご存じの通りである。
問題は、なぜ2004年の引き締め局面で長期金利が上昇しなかったのかという点である。これは米国の金融当局が既に分析済みである。ニューヨーク連銀のエコノミストであるAdrianとCrump、そしてMoenchの3人は、それぞれの頭文字をとったACMというモデルで長期金利の構成要素を分解している。すなわち、長期金利は「短期金利の期待値」と「ターム・プレミアム」に分けることができる(ニューヨーク連銀のHPで日々更新されている)。ターム・プレミアムとは、同じ期間に短期債を何度も購入する代わりに長期債を保有する際、投資家が求める上乗せ金利のこと。

グラフを見ると一目瞭然である。前回の利上げ局面では、当然のように短期金利の期待値は上昇したが、ターム・プレミアムが大幅に低下したのである。
では次の問題として、何がターム・プレミアムを低下させたのであろうか?タームプレミアムの決定要因について資料を渉猟していたら、某中央銀行のワーキングペーパーを発見した。「金融政策ルールとターム・プレミアム」という立派な論文である。それによると、ターム・プレミアム低下要因として以下のように述べられている。
<債券価格は、金利水準に対して非線形であり、金利上昇時の低下幅よりも、金利低下時の上昇幅の方が大きい。従って、金利のボラティリティが上昇した場合、債券価格の期待値が高まる。これは、債券保有者にとって好ましいことなので、ターム・プレミアムの低下要因となる。>
これは直感と違うが、一応、納得した。<債券価格は、金利水準に対して非線形であり、金利上昇時の低下幅よりも、金利低下時の上昇幅の方が大きい>というのは、通常の債券のコンベクシティがデュレーションの直線に対して凸である(正の値をとる)ということだ。簡単に言うと、金利が上下する確率が50:50であっても、価格変化は50:50とはならない。期待値がプラスなら、買いで臨むほうが有利。だからマーケットが荒れたら(ボラティリティが上昇したら)債券の買い要因(ターム・プレミアムの押し下げ要因)になるという理屈だ。なるほど、確かに僕の知り合いの元ボンド・トレーダーもリスクラバーであり、ボラティリティを好む。
ところが調べてみると、まったくその逆であった。ターム・プレミアムとボラティリティは連動している。すなわち、ボラティリティが高まるとターム・プレミアムは上昇し、ボラティリティが低下するとターム・プレミアムも低下する。これはボラティリティをヒストリカル(過去の標準偏差実績値)にしても、インプライド(オプション価格から導出した市場が内包する値)にしても同様の傾向である。
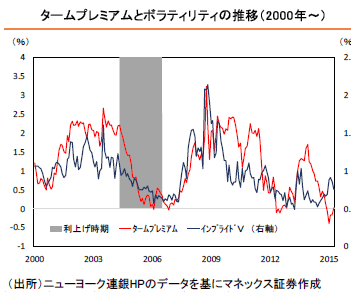
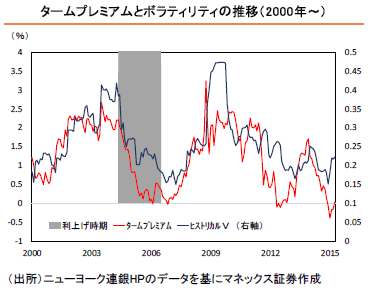
これは、ある意味、トートロージー(自己循環論法)である。FRBはそもそもボラティリティの抑制を目指していたとも言える。ターム・プレミアムとは、同じ期間に短期債を何度も購入する代わりに長期債を保有する際、投資家が求める上乗せ金利のことだと述べた。つまり、長い期間の債券を買うのは、それだけ「時間」の経過に対するリスクを負うことになる。金利リスクの最たるもののひとつは金融政策の変更だ。ターム・プレミアムとは、FRBの政策金利の不透明性に対して投資家が要求する上乗せ利回りとも言える。だからこそ、FRBは、「相当な期間」などの言葉を使って市場とコミュニケーションを図り、リスクを抑制してきた。それはボラティリティの抑制⇒ターム・プレミアムの低下⇒長期金利の低水準維持というメカニズムを利用することであった。
米国の長期金利は上昇するか
いちばん初めの問いに戻ろう。長期金利が上昇するか、である。これまで見てきたように、それはターム・プレミアムが上昇するか、を問うことに等しい。利上げが見えてくれば、長期金利の構成要素のうち、短期金利の期待値は確実に上昇する。その時に、それを相殺しない範囲でターム・プレミアムが推移すれば長期金利は上昇する。
重要なことは、ターム・プレミアムは現在、相当低い - 異常なまでに低い水準にあるということである。前回の利上げ時、長期金利が上昇しなかったのはターム・プレミアムが剥落したからであることは既に見た通りだが、当時はまだボラティリティもターム・プレミアムも両者ともに「剥げ落ちる」余地があった。ところが現在は異常なまでの低水準に既にある。2012年以降はマイナス圏に沈むこともしばしばあり、今年の1月にはマイナス40bpsを記録している。これ以上の低下余地はないと考えるのが普通である。 普通でないことも起こり得る。欧州ではドイツの国債利回りが一時、9年債までマイナス利回りになった。確かに普通では考えられない、異常なことは起こる。しかし、異常なことは長くは続かず、早晩、是正される。直近はECBのソブリンQEのインパクトでドイツ国債利回りが低下し、そのバイアスがかかった目で見ていたから世界的な金利低下が起きている印象があったが、実際には既に1月には日米ともに長期金利は大底をつけている(少なくとも現在では「大底」に思われる)。
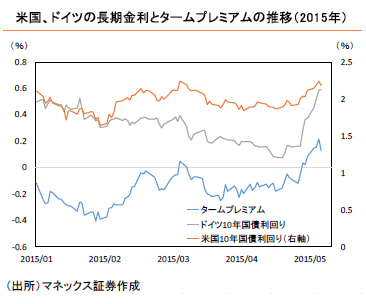
ターム・プレミアムに底打ち感があるという点が、長期金利が大底であるという理由である。なぜターム・プレミアムはマイナスにならないのか。もう一度、繰り返すと、先行きの不透明感に対して要求されるのがターム・プレミアムである。これがマイナスということは、将来は今より不透明でない、将来は今より確かだ、ということになる。それは、もはや神の領域であって、貪欲にイールドハンティング(利回り追求)に明け暮れる俗世間の話ではない。
ボラティリティもターム・プレミアムもこれ以上、低下する余地は限られている。あとは上がるしかない。今度、FRBが利上げに動くとき、イエレン議長はグリーンスパンの台詞、「Conundrum(謎)」を繰り返すことはないだろう。
(※)印刷用PDFはこちらよりダウンロードいただけます。
